心のケア・おはなし会
心療内科や心理カウンセラーへの相談も、とても大切な手段のひとつです。
一方で、同じ経験をした当事者だからこそ、話せること・伝わる想いがあると、私たちは感じています。
我が子とのお別れは、経験した人にしかわからない苦しみがあります。
その悲しみは、時間が経っても、ふとした瞬間に心を揺らします。
だからこそ、一度きりの支援ではなく、月命日やライフイベントを一緒に感じられる “伴走型のサポート”が必要だと考えています。
お父さんにもサポートを
お母さんだけでなく、お父さんにも支援が必要です。
「奥さんを支えてあげてね」
――そう言われた経験があるお父さんも多いのではないでしょうか。
でも、お父さんも同じように、大切なお子さまとのお別れに心を痛め、深く悲しんでいます。
それでも、多くのお父さんは、仕事を休むこともできず、ご自身の感情と向き合う時間も持てないまま、日々を過ごしているのが現実です。
BECAMEでは、お母さんだけでなく、お父さんにも心を寄せたサポートを届けたいと考えています。
同じ経験を持つ当事者が、お話を聞き、無償だからこそできる長期的であたたかな伴走を大切にしています。
BECAMEの心のケアのかたち
以下の方法で、気持ちに寄り添う時間をご提供しています:
- ♥ Google Meetなどを使用した 個別おはなし会(オンライン)

- ♥ 公式LINEによる 個別チャットでのご相談(※準備中)
- ♥ 複数人での おはなし会イベント・ワークショップ開催(オフライン)
ご予約・詳細については、下記よりご確認ください
Baby Loss Awareness Week の取り組み
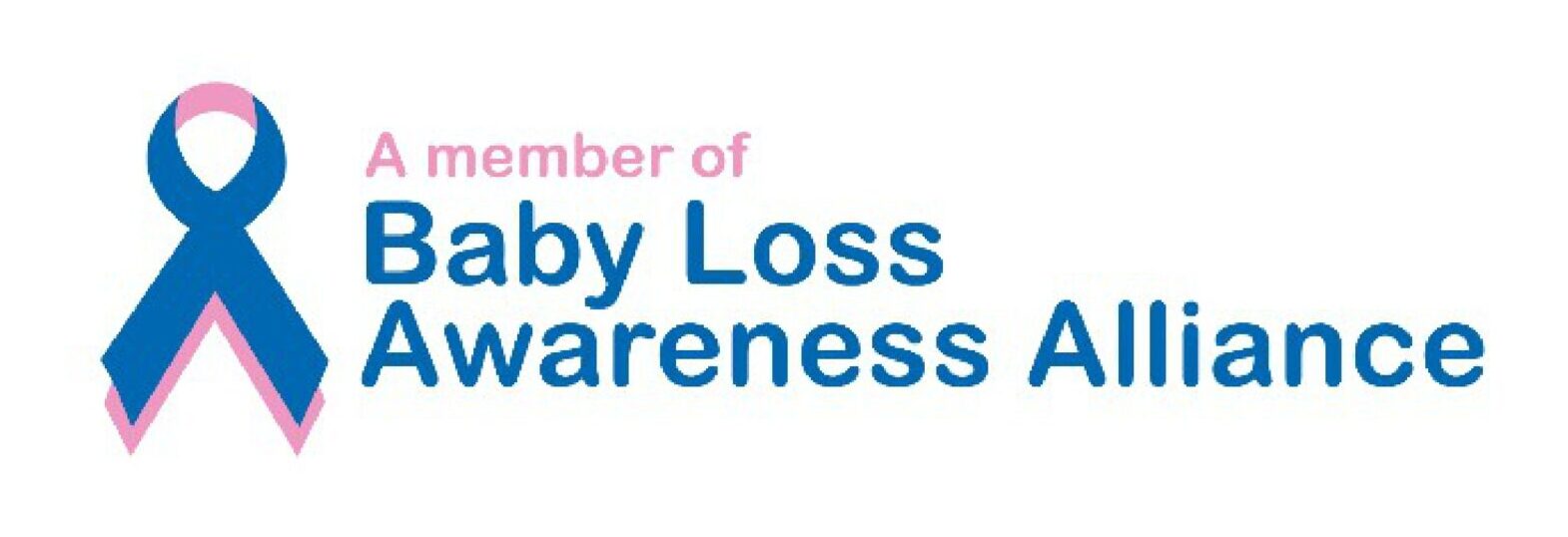
BECAMEは、Baby Loss Awareness Week(ベイビー・ロス・アウェアネス・ウィーク)の公式サポーターとして登録されています。
毎年この啓発週間にあわせて、心を寄せ合えるイベントを開催しています。
就労支援
我が子とのお別れを経験したあと、
復職・転職・退職など「仕事」に関する悩みを抱える方が多くいらっしゃいます。
お別れのあと、心と体の状態は大きく変化します。
今までのように働けなかったり、働く環境がつらく感じたり、
人と会うことさえ負担になることもあります。
一方で、
「金銭的な理由から働かなければならない」
「少しずつ前に進んでみたい」
そんな思いから、社会復帰を望まれる方も少なくありません。
しかし現実には、
“自分に合う職場が見つからない”
“人と関わることが怖い”
“心の準備が整っていない”
といった理由から、働くことが難しい方も多くいらっしゃいます。
なぜ在宅ワークなのか
BECAMEでは、在宅ワークを中心としたお仕事の紹介を行っています。
我が子とのお別れを経験したあと、
通勤中に妊婦さんやお子さん連れの方を見かけるだけでも、
胸が苦しくなることがあります。
そうした「心がざわつく場面」をなるべく避けながら、
安心できる環境で少しずつ働き始められるよう、
私たちは在宅ワークという選択肢を大切にしています。
もちろん、出社勤務をご希望の方にも、状況に応じたサポートをご提供しています。
あなたの気持ちやペースに寄り添いながら、無理のない社会復帰を応援します。
就労支援説明会のご案内
就労支援にご興味のある方は、ぜひ【個別】就労支援説明会にご参加ください。
ご希望の日時をご予約いただけます。
※ 説明会の参加は無料です。
参加したからといって、必ず働かなければならないということはありません。
どうぞ安心してご参加ください。
企業さまへ
現在、BECAMEでは就業先としてご協力いただける企業さまを募集しています。
在宅勤務や柔軟な働き方にご理解のある企業さまと連携し、
当事者の方々の「自分らしい働き方」の実現を目指しています。
ご興味のある企業さまは、下記よりお気軽にお問い合わせください。
法人様向けサービスのご案内
6人に1人が流産を、50人に1人が死産を経験するといわれている今
もしかすると貴社の中にも「我が子とのお別れ」を経験された方がいるかもしれません。
復職したものの、
- ・心が追いつかず業務に集中できない
- ・周囲の何気ない言葉や接し方に孤立を感じる
- ・自分を責めてしまう
こうした悩みを抱えながらも、日々の業務に向き合っている方が少なくありません。
BECAMEでは、従業員の皆さまが安心して働き続けられるよう、
福利厚生として導入できるカウンセリング・研修サービスを提供しています。
サービス内容(一例)
- – 流産・死産などの喪失を経験した従業員へのカウンセリング
- – 復職までの伴走型サポート(本人・上司・組織)
- – 復職後から定着までの継続的ケア
- – 組織・マネージャー向け研修(喪失への理解と接し方)
「喪失の経験」は決して特別なものではなく、すぐそばにある“かもしれない”こと。
だからこそ、企業が正しく理解し、適切に寄り添うことで、
当事者が「安心して働き続けられる職場」を実現できます。
詳しいサービス内容や導入事例は、こちらからご覧いただけます
